東京の感染者が一気に800人を超えた。
重症者も比例して増え続け、このまま行けば近いうちに集中治療用ベッドが無くなることが予想される。
この速報を見た時、10代の頃に怪我で入院した時のことを思い出した。
頭を強打し緊急の開頭手術を受けることになったのだが、その時の人間模様が今でも生々しく脳裏に焼き付いている。
死生観を決定づけた出来事の話
漫画家の表現力に感服
中学の入学間もない頃、新しい環境にも慣れ友人たちと元気に日々を過ごしていたが、ある雨の日、外で走り回れない鬱憤を晴らすように廊下を全力で走り回って遊んでいたのだが、雨が吹き込み水溜りができていた場所で足を滑らせ、勢い余って後ろにのけぞる形で全身が宙に浮いた。
あまりにも勢い強く滑ったので受け身を取るまもなく、後頭部からコンクリートの廊下に強打してしまった。
漫画の世界だと幾つもの星が頭の周りを飛び交い、目玉がビヨヨーンと飛び出すシーンだが、
本当にそうなった!
その瞬間、チカチカとカラフルな星や模様が脳裏を飛び交い、まぶたの内側に物凄い圧力を感じたのだ。もし、まぶたを閉じていなかったら眼球は間違いなく飛び出していたに違いない。
漫画家の表現力に感服した瞬間だった。
どれくらい意識を失っていたのだろうか。
気がつけば他の生徒たちが周りを取り囲み、心配そうに見下ろしていた。
フラフラになりながら自宅へ帰り横になっていたが、激しい頭痛とともに後頭部がみるみる腫れてきた。
冷たいタオルを当てていたが腫れは一向に収まらず、気がつけば拳2つ分くらい後頭部が膨張し、吐き気にも襲われるようになってきた。
実在した!?志村けん扮する看護師役のモデル
鍵っ子だったので、母親が帰宅する前に元気になってよう思い、一人フラフラとおぼつかない足取りで近くの病院に駆け込んだ。
皮下出血で膨張している後頭部に針を指し、溜まった血液を全て出し切ると後頭部のタンコブは引いてきたが、吐き気は一向に収まらず増すばかりだ。しばらく様子を見ようということになり、そのまま入院することになった。
夜、着替えを持ってきてくれた母親にいきなり怒られた。
なんで怒られたのかは未だにわからない。
数日間、ひたすら点滴を打たれるだけの日々が続いたが、吐き気は一向に収まらず、ひたすら嘔吐を繰り返していた。吐きすぎて胃液もでなくなり、終いには胃袋が出てくるような勢いで全身を痙攣させていた。さすがにここまでくると脳内出血の疑いが濃厚ということで、腰椎穿刺を行うことになった。
背骨の間に注射針を差し、出てきた髄液の色で脳内出血の有無を判別する方法らしい。
当時の一般的な病院では頭蓋骨内の出血状態を確認する手立てはなく、この方法で調べるのが一般的とのことだった。髄液の色がピンク色なら脳内出血、無色なら問題無しということだ
若い担当医曰く、
「ピンク色だったら開頭手術しなきゃだけど、タンコブの皮下出血は全部取り除けて腫れも引いてるから透明だと思うよ~」
と他人事のような説明だ。
側臥位で体を丸め両膝を抱えた状態で背骨に刺される針を想像してると、
「刺すとき動いたら大変なことになるから絶対に動かないでね~」
と緊張した瞬間
【ブスッ】
そんな音が本当にしたかどうかはわからないが、
いや、したと思う。
背骨に太い針が突き刺さって行くのを体感した。
時間が止まり、丁か半か、緊張した面持ちでその状態に耐えていた。
「あれ~?ピンク色だ~ まぁ、しばらく様子見だね」
ゆっくりと針を抜きながらのんきな口調で説明された。
(ピンク色、なのに、、、なんの処置もなく、放置、、、?)
安心感より不安感が一気に増大していった。
それから数日間、相変わらずベットで吐き続けながら過ごしていたが、担当の看護師がやたら根暗で幽霊のような雰囲気を醸し出し(志村けんがコントで扮していた怪しい看護師にそっくりだった)。
か細い声は何を言ってるのか聞き取れず、点滴の種類は間違えるは針刺しを何度も失敗するはで、両腕は醜く腫れ上がっていた。
コントなら最高に笑える場面だが、現実はそれどころではない。
この病院、かなりヤバいのではないか?
これ以上放置されてたら大変なことになると思い、当初の入院予定を繰り上げ、引き止め勧告を無視し自分の意志で退院することにした。
重症患者が元気な人を介助する
その後は自宅で療養していたが一向に吐き気が収まらないため、ただ事ではないと思った母親がホウボウ駆け回り、都内の大学病院で精密検査をすることになった。
朝イチの電車で病院へ向かう途中、車内で吐き気とめまいに襲われ倒れ込んでしまったので途中下車し、タクシーで病院へ向かうと直ちに急患扱いで診てもらうことができた。
当時、日本にはまだ数台しか導入されていないCTスキャンで頭部の断層画像を撮影することになったのだが、30分ほどで終わると言われていた撮影が1時間近く経っても終わらず、そのうち操作室内が騒がしくなり、ドタバタと何人もの足音が入室して来るのが聞こえてきた。
操作室の扉が勢いよく開き、枕元にきた医師が固定ベルトを外しながら、
「今、どんな気分? すぐ親御さんと話せるかな?」
と緊張した面持ちで話しかけてきた。
廊下に出るとベンチに腰掛けていた母親が立ち上がり、その場で出来たてのCT画像を見せられながら医師の説明を受けることになった。
撮影されたばかりのCT画像には、右側頭部の骨と脳の間に誰が見てもわかるようなこぶし大の塊の影があり、
「息子さんの今の状態は、いつ死んでもおかしくない状態です。直ちに緊急開頭手術の、」
先生の話が終わる前に、横で聞いていた母親が気絶してしまい、患者が健康な人を介抱しているという奇妙な場面となってしまった。
カーテンの向こう側
翌朝一番で緊急手術することが決まり、気絶した母親をソファーに残したまま、各種検査を行うべくストレッチャーに寝かされあちこち動き回ることになったのだが、一つ問題があった。
どの病棟もベッドの空きが無く、処置室ならなんとか手配できるということだった。
たまたまなのかどうかはわからなかったが、贅沢は言ってられない。
取り急ぎ、今夜は脳外病棟の処置室に寝かされ翌朝の手術に備えることになったのだが、術前検査を終え部屋に入ると既に先客が寝かされていた。色々な検査をしている最中、他の緊急患者が先に担ぎ込まれ場所を取られてしまったようだ。
結局、狭い処置室で横に並ばされ夜を過ごすことになったが、病室の丈の長いカーテンではなく、ベッドから下が丸見えで申し訳程度のプライバシーだけが保たれた薄いカーテン1枚でかろうじて仕切られてる状態だった。
短時間でいろんな検査をしたため、すっかり疲れ果て、グッタリと横たわっていたのだが、すぐ隣のベッドは修羅場になっている。
20代前半の男性がビルの10階から飛び降り自殺を図り、何箇所もたらい回しにされた後、この病院に担ぎ込まれてきたらしい。
正気に戻った母親が耳元で心配そうに囁いてくれた。
いつの時代もオバちゃん達の情報収集能力は世界一だ。
色々な医療機器の音が不規則に鳴り響き、医師や看護師達が必死に蘇生術を試みている。
その姿はカーテンで隔たれていたので直接視ることはできなかったが、スタッフの緊迫した声、意味不明な呻き声とともに床に広がる血痕、匂いなどで室内が満たされているため、色々な想像が脳裏を駆け巡り、ゆっくり休むどころの気分ではなかった。
消灯時間を過ぎる頃には修羅場も小康状態になったようで、トイレと気晴らしを兼ねて部屋の外に出てみることにした。
深夜の病棟は薄暗く、他の部屋からは時折聞こえる微かなイビキ以外は物音一つしない静けさに包まれおり、音を立てないようにトイレに向かい、用を足すのも音がしないように角度を調整した。
ナースステーションを覗いてみると、一人の看護師さんが黙々と仕事をしていたが、自分の姿を見つけると笑顔で話し相手になってくれた。
翌朝の手術の心配を和らげようと色々話してくれたが、何故か不思議と怖いという感情が湧くことはなく、隣の患者さんのことで頭がいっぱいだった。看護師さんの話し方が良かったのだと思うが、CTスキャン室で医師の話を聞いた時も全くの平常心で、むしろ気絶した母親の心配をしていたほどだ。
導眠剤を処方してもらい部屋に戻ると、医療機器の音は間延びしたリズムに変わっており、カーテンの隙間からは親御さんらしき女性が枕元に屈んでる姿があった。
そっとベッドに横たわり眠りにつこうとしたが、
何かを必死に詫びる親御さんの嗚咽と、それに応えるかのように時折乱れる無機質なリズム音が夜通し室内を包んでいた。
いったい、
これだけ必死に親が子供に侘びなければいけないことって、親子の間に何があったのだろう?
いったい、
どれだけ苦しい思いが募れば自ら命を断つ選択をしてしまうのか?
眠りにつこうと目を閉じたが、かえってあれこれ考え込んでしまう。
それでも中学生の頭ではとうてい想像がつかない。
今、まさに消えようとしているロウソクの炎が脳裏に浮かび、
なぜか自然と涙が溢れてきた。
、、、後編に続く、、、


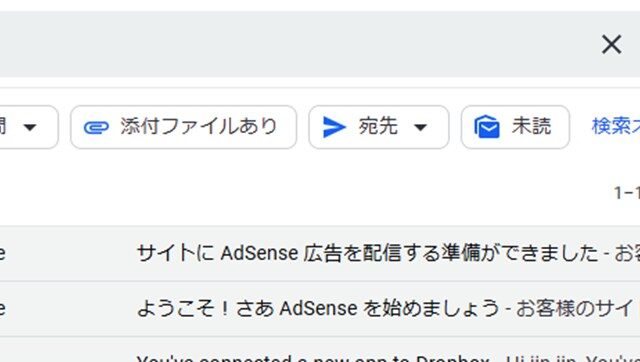






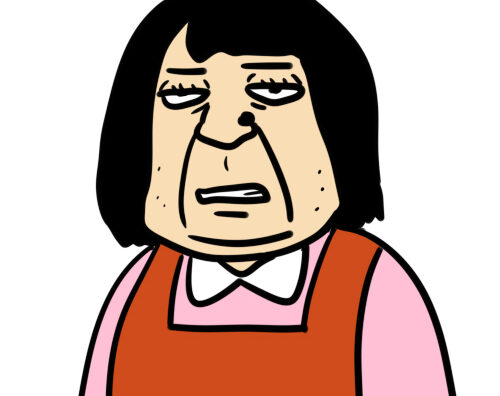




















コメント